心をひらく
テレフォン法話で配信された内容を収録した冊子です。様々な角度から「今を見つめ直す」1冊。
・頒布価格:200円
・A5版
東海地域に真宗は、12世紀の中頃に親鸞聖人が関東から京都に戻られる途中で三河国(愛知県)に滞在し、布教したことで広がったと伝えられています。
伊勢国(三重県)には、親鸞聖人の直弟子・顕智とその弟子善念が鈴鹿の三日市を訪れ布教したという伝承が残っており、応長元(1311)年には親鸞聖人の曽孫で本願寺第3代覚如上人が伊勢国に訪れています。
戦国時代になると、本願寺第8代蓮如上人が伊勢国に来訪して布教しました。その際に蓮如上人は、門徒に六字名号を授け、また御文によって真宗の教えを伝えられました。それにより、さらに真宗の教えが広まり真宗寺院の原型となる道場が各地に作られ、また、蓮如上人がすすめた門徒が念仏の教えを語り合う集まりの「御講」の原型ができました。やがて、伊勢国の門徒は本願寺の信頼を得て、「伊勢門徒」と呼ばれるようになり、重要な役割を果たす僧侶も多く出ました。
その後、元亀元(1570)年に本願寺と織田信長が対立。それに呼応して長島一向一揆が蜂起し、真宗の教えを守るため多くの門徒が戦いました。それを契機に本願寺の重要拠点であった桑名に、本願寺第12代教如上人により桑名別院が創立されます。
江戸時代になると、本願寺は西本願寺と東本願寺に分かれます。東本願寺の別院となった桑名別院には、東本願寺門首が江戸に向かう際に桑名に宿泊するなど変わらず重要な拠点でした。また、門首によって真宗の教えが書かれた手紙(ご消息)が伊勢門徒に伝えらえており、北勢地域ではこのご消息が縁となり、「御講」が盛んになりました。
今でも別院を中心に三重県では真宗の教えが受け伝えられてきています。

三重教区・桑名別院では、2026年の春に宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讚法要をお勤めします。親鸞聖人は1173年にお生まれになりました。9歳で得度(僧侶となる)し、自身の苦悩を仏道にたずねられ、師・法然上人との出遇いから念仏の教えに生きることを決意されます。のちに主著『教行信証』の草稿を完成された1224(元仁元)年が、浄土の真宗が開かれた立教開宗(りっきょうかいしゅう)の年とされました。
「慶讚」は「きょうさん」と読み、親鸞聖人の誕生と、真宗の教えを開かれたことを「慶(よろこび)」、「讃(たたえる)」という意味の法要で50年に1度勤まります。この二つの出発点を通して、800年の時を経て伝わった真宗の教えに、私たち一人ひとりが、人と生まれたことの意味を確かめなおす大切な機会であります。

211とは現在、三重教区にある真宗大谷派のお寺の数です。これらのお寺の本山は京都の真宗本廟(東本願寺)です。真宗本廟は親鸞聖人の教えを聞き、真宗の儀式をお勤めする根本道場であります。その真宗本廟からみて私たち門徒が所属し、お手次とするお寺は一般寺院と呼ばれています。
また、「+1」とは三重教区には一般寺院の他に別院があります。正式には真宗大谷派桑名別院本統寺といい、「桑名のご坊さん」と呼ばれ親しまれてきました。桑名別院は三重教区における教化の中心であり、一般寺院に先立ち真宗のお寺の在り方を示すお寺であります。別院は全国の各地にあります。真宗の教えは真宗本廟を中心に、そして別院、一般寺院を通して私たちに届いています。

お釈迦様から約2500年、親鸞聖人から800年。浄土真宗では、仏の教えを大切にして、自らの人生を仏の教えに問いたずねて生き、共に教えを聞く門に入った方を「門徒」と言います。その関係には上も下もなく、すべての人々はつながるという意味で「同朋」「同行」とも呼びあってきました。
すべての人を平等に救うという阿弥陀仏の願いを依り処として、「念仏」を生活の中心において、念仏から自分自身を照らされながら、比べることのできない“私”の人生をそれぞれに歩んできました。
その歴史と教えが、数多の先人によって、現代までつながってきました。そのことを門徒・僧侶ともに慶び讃えるとき、その声が今を照らし、後を導く道となっていくのでしょう。
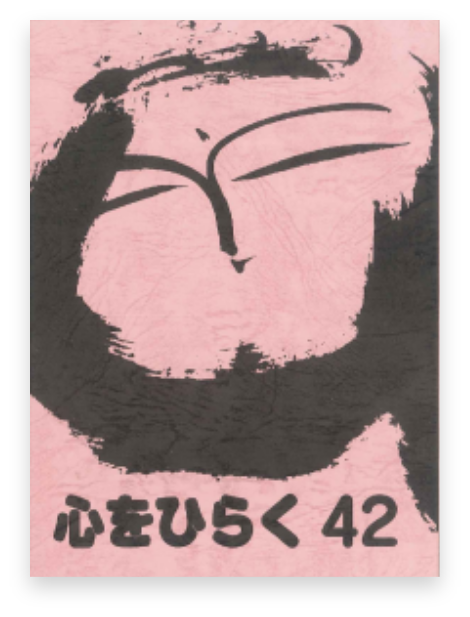
テレフォン法話で配信された内容を収録した冊子です。様々な角度から「今を見つめ直す」1冊。
・頒布価格:200円
・A5版
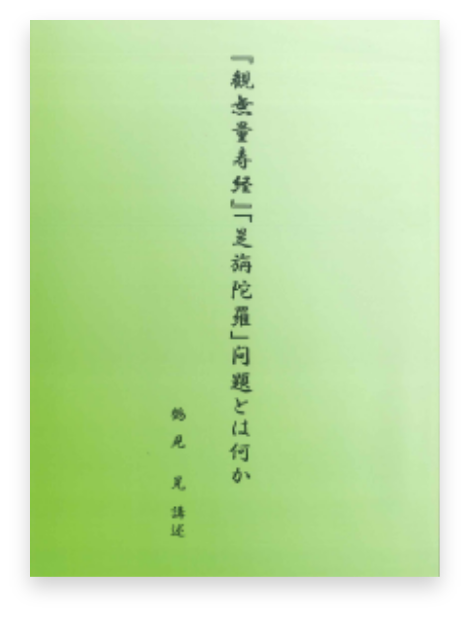
2019年に開催された「是旃陀羅問題に関する学習会」の講義録です。(鶴見 晃 氏 講述)寺院や組における学習資料としてご活用ください。
頒布価格:200円
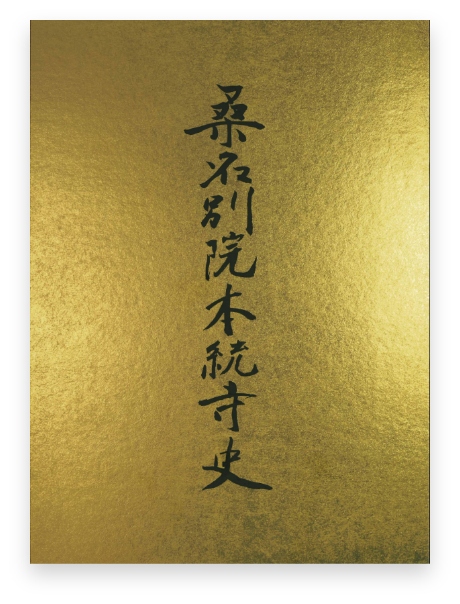
三重県の真宗伝播の歴史や一向一揆など桑名別院を支え、ともに手を合わせてこられた先達の姿や声を、次の世代へと伝えていく一冊
頒布価格:2,000円
書籍のお求めは
お問い合わせフォームへ
その他東本願寺出版サイトへ