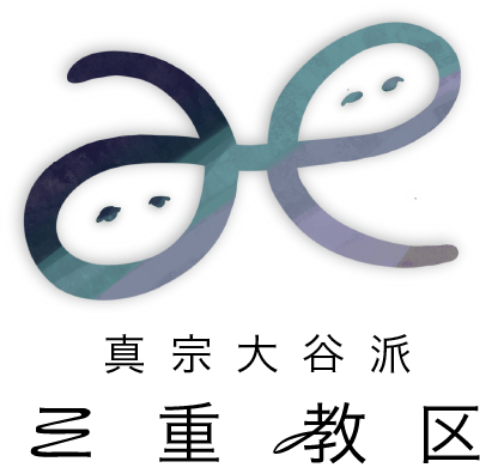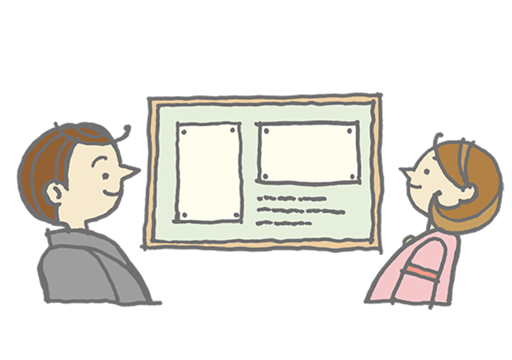伊勢・尾張・美濃の衆徒、桑名三崎に総会所を作り「今寺」と呼ばれる。
本願寺第11代顕如上人、織田信長への敵対の意を表明し各地の門末に激文を送る。それに呼応して長島一揆勢が蜂起。
桑名別院について

桑名別院は、真宗大谷派(東本願寺)の地方中心道場「別院」の一つです。
正式名称を真宗大谷派桑名別院本統寺(くわなべついんほんとうじ)と言い、1596(慶長元年)年、本願寺第12代教如(きょうにょ)上人開創されたと言い伝えられています。
それ以来、三重の門徒にとって、親鸞聖人の教えを聞き、生きることの意味をたずねる大切な「聞法の中心道場」として受け継がれてきました。
桑名別院の歴史

元亀・天正の間、石山本願寺と織田信長は後に本願寺十年戦争といわれる騒乱の中で幾度となくぶつかり合ってきました。
当時、伊勢・尾張・美濃の三国の水陸の交通の要所であった桑名の地は、長島一向一揆をはじめとする真宗の一大法難の時期に直面していました。本願寺第11代顕如(けんにょ)上人は、桑名(当時の名称は三崎(みさき))に「今寺(いまでら)」と称された「寄合所(よりあいじょ)」を草創し、本山との連絡、諸種の法務、非常時の際の協議集合の場所が桑名別院のはじまりです。
そして、争乱終結後の1596(慶長元)年、本願寺第12代教如上人によって、この「今寺」を本願寺の禄所(ろくしょ)として取り立てられ、1641年、桑名別院の本堂が建立されます。
開基は、教如上人の娘である長姫(おさひめ)とされております。しかし当時、長姫は9歳であったため、石川県小松の勧帰寺(かんきじ)の玄誓(げんせい)が寺務を執りました。その後は、寿量院宣慧(じゅりょういんせんね)、第3代慧浄院琢慧(えじょういんたくえ)へと引き継がれ、慶安2(1649)年5月4日、「本統寺」と改称され、長きに渡り三重の門徒衆にとって大切な聞法の中心道場であり、儀式の場となっていきます。
その後、延宝年間(1673~1681)に堂宇(どうう)は失火により焼失してしまいますが、1686年、桑名の長者である山田彦左衛門の一寄進により、雄大な八棟造りの本堂をはじめ、対面所、書院等が再建されました。
しかし、昭和20(1945)年7月の二度にわたる桑名大空襲により、桑名別院の本堂をはじめ、山門、鐘楼堂、書院などが焼失してしまいます。しかし、境内に建つ親鸞聖人の銅像と灯篭一対、芭蕉の句碑は戦災を免れました。ただ、銅像の菅笠を下から見上げると小さな穴が空いているのが見えます。これは空襲の際の焼夷弾の破片が貫通したものと言い伝えられています。
また、別院の御本尊・宗祖親鸞聖人・蓮如上人・厳如上人・彰如上人・ 双御影・太子七高僧の各御影は、空襲の直前に避難をさせていてことに無事でした。
昭和20(1945)年8月15日に終戦を迎えると、焼失を免れた親鸞聖人の銅像の横にバラック小屋を建て、その小屋と専明寺(桑名市東方)に仮の寺務所を設置して、寺務の整理にあたりました。翌9月、現在のいなべ市に避難していた御本尊を専明寺に遷座し、そこを仮御堂として終戦からわずか5か月後の12月21日から二昼夜にわたって報恩講が厳修されました。また、その頃には、別院復興の多額の御懇志が寄せられており、戦災にあった人たちからの尊い寄付をいただきました。その大切な御懇志をもとに現在の別院が復興されます。本堂は、京都の新京極にあった金蓮寺という時宗のお寺の本堂を譲り受けて移築したものです。
また鐘楼堂と山門は、大阪府八尾市の八尾別院大信寺から譲り受けたものです。
その後、50年を経て雨漏りなど著しい老朽化が見られたため、平成13(2001)年にされた「五百回法要」の記念事業として、本堂をはじめ諸殿の修復、「大玄関」と多目的に活用できる「聞光殿」を新築しました。
また、平成26(2014)年の「三重教区・桑名別院七百五十回」の記念事業として、本堂の修復、別院の耐震化・瓦のきえ、三重屋根の修復等が行われ、桑名別院が今後も聞法の中心道場として歩み続ける役割が果たされることが願われています。
桑名別院の沿革
元亀元年(1570年)
元亀2年(1571年)
5月、織田信長第1次長島侵攻。
天正元年(1573年)
9月、織田信長第2次長島侵攻。
天正2年(1574年)
7月、織田信長第3次長島侵攻。長島城陥落。長島一向一揆終結。
慶長元年(1596年)
本願寺第12代教如上人「今寺」※1を伊勢・尾張・美濃の3国の禄所として取り立てる。桑名御坊と呼ばれる。
教如上人、息女、長姫を事務職として桑名に派遣する。
長姫は9歳であったため、小松(石川県)歓帰寺の玄誓が寺務を執る。
慶長8年(1603年)
徳川家康、征夷大将軍に任官。江戸幕府が始まる。
寛永元年(1624年)
本願寺第13代宣如上人嫡男、寿量院宣慧(本統寺第2代)、長姫の養子として桑名御坊に入寺。
寛永18年(1641年)
桑名御坊本堂建立。
寛永20年(1643)
7月26日、寿量院宣慧(本統寺第2代)亡くなる。
12月17日、長姫(本統寺初代)亡くなる。
慶安2年(1649年)
5月4日、桑名御坊、「本統寺」の寺号を授かる。
慶安3年(1650年)
4月25日、本願寺第14代琢如上人次男、慧浄院琢慧(本統寺第3代)桑名本統寺に入寺。
寛文5年(1665年)
8月16日、失火により、桑名本統寺焼失。
貞享元年(1684年)
松尾芭蕉、桑名本統寺に宿泊。
貞享3年(1686年)
豪商、山田彦左衛門の一寄進により本堂再建。
間口15間2尺、奥行14間4尺、八つ棟構造の壮大な建築。
元禄3年(1690年)
琢如上人六男、深広院常智(本統寺第4代)、本統寺入寺。※2
宝永6年(1709年)
慧浄院琢慧(本統寺第3代)亡くなる。
享保2年(1717年)
深広院常智(本統寺第4代)亡くなる。
嘉永元年(1848年)
本願寺第20代達如上人三男、深量院達智、本統寺に入寺。
病のため明治2年(1869)退隠。
明治13年(1880年)
明治天皇、御巡幸の際、行在所となる。
明治20年(1887年)
本願寺第21代厳如上人四男、慧日院厳量、本統寺住職に就任。
昭和20年(1945年)
7月、2度にわたる桑名大空襲により、桑名本統寺焼失。
昭和25年(1950年)
本堂及び、諸施設が再建される。
本堂→(京都府下)時宗寺院から譲り受ける。
山門・鐘楼堂・南北門→八尾別院(大阪府)から譲り受ける。
庫裡→海津(岐阜県)の豪農、菱田氏より譲り受ける。
昭和26年(1951年)
6月26日、慧日院厳量、亡くなる。
昭和29年(1954年)
慧照院瑩俊、本統寺住職に就任。昭和33年(1958)辞任。
昭和33年(1958年)
本願寺第24代闡如上人、本統寺住職に就任。
平成8年(1996年)
本願寺第25代浄如上人、本統寺住職に就任。
令和2年(2020年)
本願寺第26代修如上人、本統寺住職に就任。
※1 本山との連絡・諸種の法務・非常時の際の協議集合の便を図るため草創された坊舎。
※2 元禄4(1691)年3月、輪番勤務の別院となり、御連枝住職廃絶。天保10(1839)年古制に復す。なお現在は輪番制。
松尾芭蕉と桑名別院
冬牡丹
千鳥よ雪の
ほととぎす
[ 訳 ] 千鳥を聞きながら、雪中に牡丹とは、なかなか見られない光景であるよ。
今の今まで、牡丹とくればほととぎす、と思っていたのに

江戸時代には、当時の住職(3代)がにが深かった縁で、時の桑名藩主松平定重(まつだいらさだしげ)との交流も深く、そのことからともがあり、芭蕉が桑名別院に宿泊し、この句を詠んだと伝えられています。
桑名別院マップ





桑名別院の主な年間行事・法要
毎日の行事
-
晨朝(おあさじ)
午前7時~8時 勤行後法話
-
祥月申経
午前9時~9時30分
※毎月13・28日は午後1時~ -
お夕事(おゆうじ)
午後4時~4時30分
毎月の行事
-
先門首ご命日法要
毎月12日午後1時~逮夜 / 毎月13日午前7時~晨朝 / 毎月13日午前9時~日中
-
親鸞聖人ご命日法要
毎月27日午後1時~逮夜 / 毎月28日午前7時~晨朝 / 毎月28日午前9時~日中
-
法話のつどい
毎月13日午後1時~2時半(勤行と法話)
-
ご命日のつどい
毎月28日午後1時~2時半(勤行と法話)
-
人生講座
毎月第1日曜日午前7時~8時
-
別院同朋の会
毎月第1金曜日午後1時~2時半
月ごとの行事
-
1月
修正会
1月1日〜3日
-
3月
春季彼岸会
春分の日含め7日間
-
4月
花まつり
4月8日
-
6月
真宗公開講座
6月頃(会場は中南勢地区)
夏の御文
6月27日・28日
-
7月
孟蘭盆会
7月14日・15日
暁天講座
7月中旬5日間
-
8月
墓地総経
8月13日
-
9月
秋季彼岸会
秋分の日含め7日間
-
12月
報恩講
12月20日~23日
歳末勤行・除夜の鐘
12月31日